一戸建て住宅やマンションの床のフローリングは、大きく「複合/複層フローリング」と「無垢フローリング」の2種類に分けることができます。
それぞれ良さと特徴があるため、一概にどちらがいいとは言えません。
今、家づくりやマンション購入を検討されている方、そして、床のリフォームを検討している方は是非、複層フローリングと無垢フローリングの違いを知っておいて損はありません。
複層フローリングと無垢材の特徴、そして、メリットとデメリットを比較することで、より家族のライフスタイルにマッチする床材が見つかるはずです。
![[窓]+ガラスフィルムで快適空間-ガラスフィルムが室内の様々なお悩みを解決。プロ業者が施工する、ガラスフィルムのラインアップ。](https://www.film-work.com/wp-content/uploads/2022/05/banner-film-info-3.jpg)
複合/複層フローリングと無垢フローリングの違い
| – | 複合/複層 フローリング | 無垢 フローリング |
| 質感 | やや低い | 高い |
| 床の温かさ | やや冷たい | 温かい |
| 調湿性 | 低い | 高い |
| 耐久性 | 無垢材より低い | 高い |
| 耐傷性 | 高い | 低い |
| 防汚性 | 高い | 低い |
| 音 | 出にくい | 出やすい |
| 静電気 | 発生しやすい | 発生しにくい |
| 接着剤 | 使用 | 未使用 |
| 施工の 難易度 | 低い | 高い |
| 価格 | 安価 | 高価 |
複合/複層フローリング
複合、複層フローリングとは、合板に化粧板を接着剤で固めた床材を意味します。
複合/複層フローリングの種類

複合/複層フローリングは大きく「挽き板フローリング」「突き板フローリング」「シートフローリング」に分かれます。
挽き板フローリング
挽き板とは、原木を2~3mmの厚さにカットし、合板の上に貼り付けた板。
突き板フローリング
突き板とは、原木を1mm以内の薄さでスライスし、合板に貼り付けた板。
シートフローリング
シートとは、樹脂などに木目模様を印刷し、合板に貼り付けた板。
複合/複層フローリングのメリット,デメリット
メリット
・キズが付きにくい
・汚れが付きにくい
・合板のため、踏んでも音が出にくい
・安価
デメリット
・質感が無垢材に及ばない
・ウレタン塗装のため、冬季は冷たさを感じる
・表面のひび割れなどで、無垢材より耐久性が低い
・ウレタン塗装のため、静電気が発生しやすい
複合/複層フローリングのまとめ
10年前と今の複合/複層フローリングを比較すると、明らかに表面の質感が向上しています。離れた場所から複層フローリングを見ると、無垢材と区別ができないほど。
もちろん、近くで見た複層フローリングの質感は無垢材には及ばず、表面が塗装されているため人工的な印象を受けます。
しかし、複層フローリングは汚れにくく、キズが付きにくい大きな特徴あります。複層フローリングは子供が室内で走り回り、おもちゃを投げたり落としたりするような環境に比較的、強いと言えます。
無垢フローリング
無垢材のフローリングとは、木をスライスして加工した床材を意味します。要は、加工された1枚板。単層フローリングとも呼ばれる無垢フローリングの断面に木の年輪を確認できます。
無垢フローリングの種類
無垢材にはいくつかの種類があり、木目と風合いが異なります。
【柔らかい木】杉、パイン、桧(ヒノキ)


【硬い木】サクラ、楢(ナラ)、ウォールナット、メープルなど

無垢フローリングのメリット,デメリット
メリット
・質感が高い
・床の表面が温かい
・静電気が発生しにくい
・50~100年の耐久性
・表面をカンナで削ることができる
デメリット
・キズが付きやすい
・汚れが付きやすい
・幅の狭い1枚板を複数枚、貼り合わせるため木が伸縮し、踏むことで音が出やすい
・高価
無垢フローリングの価格が高くなる理由として、無垢材の価格+大工さんが幅の狭い無垢材を1枚1枚、床に貼り付ける手間がかかるため。
しかも、無垢材は伸縮する理由から、板と板の間にわずかな隙間を設けて施工する必要があります。このような理由から、無垢材の床はコスト高となります。
無垢フローリングのまとめ
子供やペットが汚れた足のまま室内を走り回ると、無垢材に汚れが付きやすくなります。また、床に物を落とすとキズや凹みが付きやすいのが難点です。
しかし、無垢材ならではの質感と温かさ、耐久性は複層フローリングには無い大きな特徴です。
子供が成長し、床の汚れやキズの心配が無くなった家の床をリフォームするならば、無垢フローリングは選択肢の1つです。
フローリングの張り替えはDIYで可能?それとも業者に依頼?

DIY
床のリフォームを検討中の方で、DIYでフローリングの張り替えを検討している方もいることでしょう。
必要な工具類
DIYでフローリングを張り替えるとなると最低限、丸ノコギリ、電動ドライバー、ハンマー、木製ハンマー、カンナ、ノミ、さしがね、メジャー、カッターなどの工具類が必要です。
ホームセンターなどで電動工具を借りることで、費用を抑えることができます。あと、クギとネジ類も必要です。
材料
フローリング床材の種類は膨大なため、まずは無垢フローリングにするのか、それとも、複層フローリングにするのか決める必要があります。
失敗のリスク
もし、あなたが生まれて初めてDIYでフローリングの張り替えにチャレンジするとなると、作業の難易度は高いと言わざるを得ません。
工具類と材料を仕入れ、フローリングの張り替えにチャレンジしたものの、途中で失敗してしまうと諦めるしかありません。結果的に業者に張り替えを依頼せざるを得ない場合もあります。
その場合、工具類や材料費がムダになってしまい、時間も大きくロスしてしまいます。DIYでフローリングの張り替えは、DIYの経験が長く、技術を持っている方を除いてお勧めできません。
業者に依頼
費用
業者に床の張り替えを依頼すれば、明らかに工期が短くて作業が確実。餅は餅屋です。
そこで、業者にフローリングの張り替えを依頼する場合、工法が2種類あります。以下の費用は、あくまで目安です。フローリングの床材によって、リフォーム費用は前後します。
張り替え工法
今の傷んだフローリングを剥がして、新しいフローリングを張り付ける工法。基本的な工法です。
重ね張り工法
今のフローリングの上から新しいフローリングを張り付ける工法。床に段差が発生するデメリットがあります。
| 畳数 | 張り替え | 重ね張り |
| 6畳 | 9~18万円 | 6~14万円 |
| 8畳 | 10~20万円 | 8~18万円 |
| 10畳 | 12~22万円 | 10~22万円 |
家族構成の変化と家の寿命の関係
複層フローリングのメリットの裏返しが、無垢フローリングのデメリットになります。
無垢フローリングのメリットの裏返しが、複層フローリングのデメリットになります。
ここで、人が家に何年住むのか、長期的な視野で考えてみます。
世の中、100年の耐久性をPRしている家が存在します。しかし、30代の方が家を建て、その家に100年間、住むことは不可能です。人の寿命より、100年住宅の方が寿命が長いのです。
100年の耐久性がある家とは、親の子供がその家に住む前提の家と考えることもできます。
ただ、親の子供(長男や長女)が成人し、その家で暮らす保証があるの?と問われたら、返答に窮するのではないでしょうか?
長男が社会人になると、就職先によっては自宅通勤は不可能であり、会社付近のアパートや寮などで生活します。長女も同様です。そして、長男の就職先によっては、転勤の問題があるでしょう。
とすると、長男は親が建てた家で生活できるかどうか未知数なのです。そして、長女は結婚して嫁いでいきます。子供たちの成長と共に、家族構成が変わっていきます。
ここで、改めて100年の耐久性がある家が必要なのか?という疑問が浮上します。そして、メンテナンスすれば、50年から100年の耐久性がある無垢フローリングが必要なのか?という疑問も浮上します。
もちろん、無垢フローリングの美点は耐久性だけではありません。無垢材ならではの質感と温かさは魅力的な特徴です。
まとめ
家に住む人のライフスタイルや家族構成、価値感によって床材の好みが分かれます。
結論として、床の暖かさを考えると「無垢フローリング」に軍配が上がります。複層フローリングは表面が塗装されているため、どうしても表面が冷たく感じるのです。
そして、床のキズや汚れに対する強さでは「複層フローリング」に軍配があがります。コスト面でも有利です。
フローリングは、どの選択が正しい、正しくないという資材ではなく、嗜好品的な要素も含んでいます。
実際に自分の目で複層フローリングと無垢フローリングのサンプルを見て、触り、木の模様と色、価格を含めて総合的に判断してはいかがでしょうか。
フローリングの色褪せ、劣化対策

複層フローリングと無垢フローリングは直射日光を浴び続けると、日焼けによる色褪せと劣化が進行します。
せっかく家族で話し合って決めたお気に入りのフローリングだからこそ、直射日光からフローリングを守ってあげたいもの。
フローリングなどの床材を直射日光から守る紫外線対策として、最も効果的なのは窓ガラスにUVカットガラスフィルムを貼り付ける方法です。
UVカットフィルムで紫外線対策

紫外線には、紫外線A波(UV-A)と紫外線B波(UV-B)が含まれています。
【UV-A】
UV-Aは肌のシミやシワ、たるみなどの原因になります。
【UV-B】
UV-Bは肌の日焼けの原因になります。
フローリングがUV-AとUV-Bを浴び続けることで、日焼けによる色褪せと劣化が進行します。
そこで、窓ガラスにUVカットフィルムを貼り付けます。
プロが使う建築用UVカットフィルムは室内に入り込むUV-AとUV-Bを99%以上カットできます。よって、複層フローリングと無垢フローリングの日焼けによる色褪せや劣化を抑制できます。
同時に、お気に入りの家具類、調度品を紫外線から守ることができます。
更に、台風による飛来物が窓ガラスを直撃しても、UVカットフィルムがガラスをしっかり保持してくれます。
【関連記事】
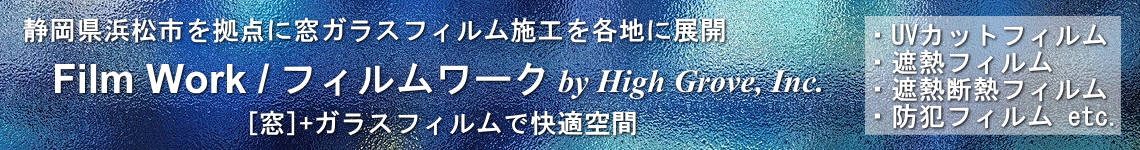


![[窓]+ガラスフィルムで快適空間-目隠し、遮熱、断熱、防犯、UVカット、抗ウイルス、防虫、飛散防止フィルムで室内空間のお悩みを解決。](https://www.film-work.com/wp-content/uploads/2022/05/banner-film-info-4.jpg)
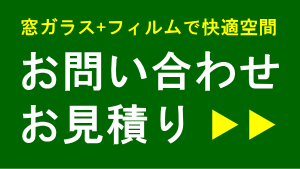


コメント